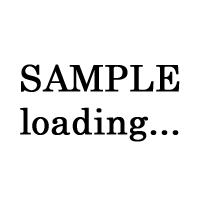
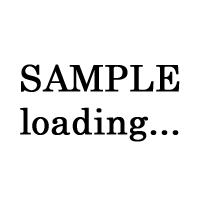
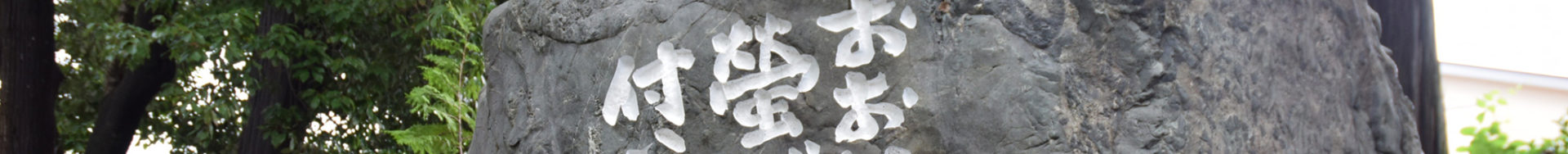
秩父札所をつなぐ道は信仰の道であるとともにさまざまな人や情報が行き交う道でもあり、巡礼者や旅芸人をはじめ、国学者や医者、俳人、歌人など文化人の姿が多く見られました。彼・彼女らの活動は地芝居や角力(すもう)興行の記録として残されており、また秩父郡に現在も残る歌舞伎や人形浄瑠璃として伝えられています。
俳諧についても幕末頃、農民の間では農閑期を中心とした俳句づくりが流行していたようで、明治以降、本格的に文芸活動に携わる人物も現れました。
秩父音頭を全国に広めた金子伊昔紅もそのような存在ということができ、俳人であると同時に、一般向けに柔剣道場や漢学を学ぶ場を設けた教育指導者でもありました。伊昔紅が皆野町で俳句会を催したのは昭和8年頃といわれており、秩父音頭が世に出るきっかけとなった明治神宮遷座10周年記念祭と時期が重なります。
伊昔紅の活動は、後に長男である兜太(とうた)に「七人の侍」と称された「七彩(しちさい)会」を結成した潮夜荒(うしお やこう)や岡紅梓(おか こうし)をはじめとする皆野の俳人を産み、俳誌「若鮎」をはじめ、昭和31年まで200号を数え秩父の俳壇を先導する役割を担った「雁坂」として結実します。一方で伊昔紅は水原秋櫻子の新興俳句運動に当初から共感しており、石田波郷や加藤楸邨をはじめとする俳人とも交流がありました。
伊昔紅は「雁坂」廃刊に寄せて「会員の俳句水準は、地方俳句としては相当高いところにありました。当初側面から指導していただいた人達は、現在では新しい俳句の先頭に立つ錚々たる顔ぶれであり(中略)中央俳壇に押し出すこともそう難事ではなかったと思っております。然し私は最初からそう云う考えは持ちませんでした。飽くまで地方誌として、初心者の鍛錬の場を提供することで満足しておりました」と述べています。地方誌に徹する、この信念が俳句の町みなのを産んだといえるでしょう。
金子兜太は金子伊昔紅の長男として大正8年(1919年)に小川町で生まれました。俳人である伊昔紅の活動が兜太を俳句の道へ導いたのは自然といってもよく、旧制高等学校時代には加藤楸邨を師として「寒雷」に投句しています。
大学卒業後は日本銀行入行を経て海軍主計中尉に任官、南洋のトラック諸島で第二次世界大戦を経験しました。戦火や餓死により多くの同僚や部下を失うという体験が、戦後の俳句活動の原点となります。戦後は日本銀行に復職して組合活動に身を投じ、社会性俳句を次々と投句しますが、1960年代初頭の「有季定」「花鳥諷詠」への回帰運動をきっかけとして「海程」を創刊。妻・皆子に土で生きるようにすすめられて東京から熊谷へ転居し、小林一茶をはじめとする古典研究を通じて人間を含む自然の本源、いきものとしての人間の姿を見つめる視点を得ました。