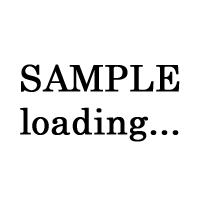
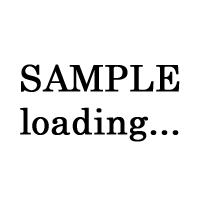
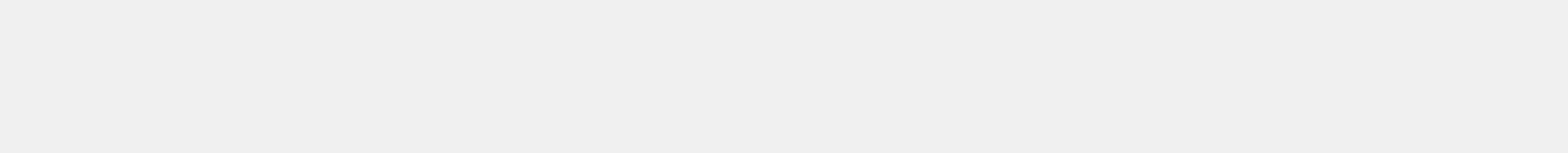
2021年10月4日(月)~29日(金)役場内庁舎ロビー
令和3年2月4日、金子伊昔紅氏の住宅兼医院であった旧壺春堂(こしゅんどう)醫院主屋・土蔵が国の登録有形文化財に登録されたことをきっかけに収蔵資料の整理が開始され、俳誌や日記、色紙などが見つかりました。皆野町内には俳句に関する資料が数多くありますが、壺春堂でその資料がまとまった形で見つかったことは、町の俳句の歴史をたどる上で大きな意義を持つものです。資料整理は現在も続いていますが、本企画展では、その成果にもとづき、町の俳句の歴史を数回に分けて紹介します。第1回では、上海時代に伊昔紅が『断層』に掲載した「驢馬(ろば)の鈴」にはじまり、昭和7年の俳誌『若鮎』創刊を経て、昭和16年の京大俳句事件までの15年余について、町内外の俳人や団体との交流に焦点をあてて紹介します。本企画展が皆さまにとって、町内俳句の新たな一面を知るための、一助となれば幸いです。末筆になりましたが、本企画展開催にあたり、貴重な資料を快くご提供いただいた皆さまに深く感謝申し上げます。
金子伊昔紅は大正4年に京都府立医学専門学校を卒業後、京都府下岩倉病院に勤めた後、大正8年から14年まで上海東亜同文書院の校医として勤めます。俳句集『秩父ばやし』によれば、伊昔紅が俳句の創作を始めたのは上海生活の後半からとされ、『ホトトギス』に投句していたことも記されています。壺春堂には大正8年から昭和8年までの『ホトトギス』が収蔵されていますが、大正年間に4句、昭和5年に1句、計5句の伊昔紅の作品が掲載されています。また大正14年に上海東亜同文書院文芸部から刊行された文芸雑誌『断層』には、北京や南京を旅した際の感想や作品が「驢馬の鈴」と題されてまとめられています。俳句を作り始めた時期の貴重な資料といえるでしょう。この頃の伊昔紅の作品について、金子兜太は『秩父ばやし』の跋(おくがき)で、処女句集である『秩父ばやし』は『馬酔木』に加わってからの作品が中心で、『ホトトギス』投句期のものは一部にすぎないとし、「父は『馬酔木』以前の自分の作品にあまり価値を置いてないのではないか」と記しています。
文学としての俳句を掲げ、俳句の改革に取り組んだ正岡子規が死去した明治35年以後、俳誌『ホトトギス』は高浜虚子が運営していました。この時期は河東碧梧桐が率いる新傾向運動へ同調する俳人が多く、『ホトトギス』の俳壇での地位は劣勢でした。虚子は夏目漱石の「吾輩は猫である」など俳句以外の作品も掲載することで『ホトトギス』の存続を図ります。大正年間になると、破調や自由律へと進んだ新傾向運動への反発が大きくなり、『ホトトギス』は大正二年の雑詠欄再開を機に俳句専門誌として再スタートを切ります。これ以降、俳壇は『ホトトギス』を中心に展開し、飯田蛇笏、村上鬼城などの第一期黄金期を経て、4Sと称される水原秋櫻子、高野素十、山口誓子、阿波野青畝による第2黄金期を迎えます。この間、虚子は安易な主観を排し、客観写生にもとづいて花鳥風月を詠む「花鳥諷詠」を俳句の根幹とします。
昭和7年5月、壺春堂から俳誌『若鮎』が創刊されます。『若鮎』と同時期の俳誌で、壺春堂に2冊残っている『柏っ葉』の裏表紙には「昭和七年五月十二日 第一回俳句会 伊昔紅金子先生宅ニテ」とペンで書かれています。『若鮎』は、この俳句会をきっかけに誕生したのかもしれません。この頃、秩父郡内にはすでに多くの俳誌が存在していました。古くは伊昔紅が上海に居住していた大正13年に創刊された「柞(ははそ)」があり、昭和5年には秩父農林学校から「耕人」、当時の秩父町から「甲望」が刊行されます。尾田蒔には「絡車」がありました。このうち昭和11年1月の「耕人」俳句展覧会号では、校内で開催された第五回俳句大会の様子を伝えています。この大会は「我が地方俳壇の一行事」として秩父夜祭と並行して開催されたもので、池内たけしや、後に吉田の天幸禅院で『二合庵日記』を記した岡安迷子が入選句の選考を行い、応募数は2800句に及んだとされます。当時の秩父俳壇の盛況ぶりを示すものといえるでしょう。
『若鮎』という本格的な俳誌がここ皆野町で誕生し得たのは、秩父俳壇という豊かな土壌があったためといえます。また秋櫻子の『馬酔木』誌上での活躍が大きな刺激になったことも間違いないでしょう。『若鮎』創刊2年目である昭和8年11月号の「壺春堂夜寒記」では、大渕の宮前百鈴の作品が『馬酔木』新葉抄に掲載されたことを伝え、「同人諸君の作句が漸次中央俳壇に認められて来たことはお互の為にも、わかあゆ存在の為にも御同慶の至り」と書かれています。『若鮎』終刊の年である昭和9年の9月号には、後に大陸で前線俳句を作り、武漢で戦死した児玉郡種足村の武笠美人蕉や、同じ児玉郡の塩崎晩江里の名が見えています。両氏ともに『馬酔木』新樹集の常連であり、『若鮎』が地方俳誌として順調に成長していたことを伺わせます。同じ年の12月号では『馬酔木』同人である篠田悌二郎の「来秩歓迎句会」として、宝登神社社務所で催された句会の特集が組まれています。中央俳壇との交流が積極的に図られていたことが分かります。
秋櫻子は『馬酔木』昭和8年10月号に発表した「三峰山その他」で、秩父鉄道を乗り継いで三峯山へ登った際のことを書いています。列車が皆野駅に停車した際には「旧友金子伊昔紅君が住んでいる土地なので特になつかしく、私は帰途ここに下車して同君を訪ねるつもりでいた」としつつ、「金子君は中学の同窓で、卒業後二十五年一度も会ったことはない」と書いています。一方で『秩父ばやし』後記によれば、伊昔紅は、皆野への医院開業に先立ち東京帝大医学部で受講した産科学講習で、秋櫻子と再会したとしています。その際に秋櫻子は、伊昔紅が上海から『ホトトギス』へ投句していたことも知っており、大学の月例句会へ出席するように勧めたといいます。いずれにせよ、この時期に両者には深い交流はなかったと思われます。
「三峰山その他」から4年後の昭和12年、俳誌『初鴨』10月号に秋櫻子と伊昔紅が長瀞に遊んだ際の様子を描いた「金子伊昔紅」(秋櫻子著)と「秩父だより」(秩父馬酔木会 潮夜荒著)が掲載されます。秋櫻子は「金子伊昔紅」のなかで「伊昔紅金子元春の如き勇猛の士を友達に持つことは、僕の頗る心丈夫に思ふところである」と記しています。『初鴨』は昭和11年に創刊された篠田悌二郎主宰の俳誌で、昭和12年7月号の「新同人欄」には夜荒と百鈴の名が記されています。
昭和12年、『馬酔木』から派生した『樹林氷』と『馬』が統合され俳誌『鶴』が創刊されます。主宰の石田波郷は昭和7年に松山から上京し、同年中には作品が『馬酔木』新樹集巻頭に選ばれるほどの才能の持ち主でした。後に秩父は「『鶴』でも全国一を誇る強力な支部となり、秩父織物組合関係者を中心に一時は50人に近い会員を擁する」(石塚友二「壺春堂翁と私」『秩父ばやし』所収)までになり、波郷自身も繰り返し秩父を訪れることになります。『若鮎』創刊後、地方誌として着実に力をつけた皆野俳壇は、秋櫻子との長瀞の再会を経て、中央俳壇との深いつながりを得ることになりました。
昭和6年、秋櫻子は俳誌『馬酔木』上に「自然の真と文芸上の真」を発表し、『ホトトギス』から離脱します。写生がそのまま風雅・風流という感情を表す作品を理想とした虚子に対し、秋櫻子は、写生はひとつの態度にすぎないこと、また人間が持つ多様な感情を作品に表現してこそ俳句は本当の文学になると訴え、若手俳人を中心に多くの共感を得ました。『馬酔木』へ拠点を移した秋櫻子は、山口誓子(昭和10年から『馬酔木』同人)などとともに新しい俳句の姿を模索します。あらかじめ定められた主題にしたがい、作品を絵巻物のように並べていく連作俳句や、スケート・法廷・水泳大会など、花鳥風月とは全く異なる題材を用いた作品などはその成果といえます。これらの試みにより、俳句は風流や風雅にとどまらない、自分の感情を自由に詠む文学(=「十七文字の詩」)として認識されるようになり、関東大震災後に誕生した帝都東京に代表される近代都市で生活する勤労者を新たな詠み手として獲得しました。その結果、季節感(=季語)に代えて都市特有の風景やモダンな感覚を作品の中心に置いた無季俳句が生まれます。これに関して、秋櫻子は「機械そのものの現象や大工場内の現象や地下深いところなど季的生活の全くないものに美を感じた場合ですら、必ず四季の支配に及んでいるにちがひない。」(『馬酔木』昭和10年3月号)と述べています。俳句の独自性を担保するのはあくまでも季節感(=季語)であり、それを失えば俳句は形だけの詩に陥ってしまうという危機感がうかがえます。この後、新興俳句運動は『馬酔木』を中心とする有季派、無季作品を積極的に詠む無季派、俳句のひとつのあり方として認める無季容認派へ分かれていきます。
昭和13年10月27日、『若鮎』にも投稿していた美人蕉が武漢攻略作戦で戦死します。伊昔紅は、多くの戦争俳句の切り抜きとともに、美人蕉戦死の一報を日記に貼り付けています。戦死から2年後の昭和15年には『武笠美人蕉句集』が200部限定で刊行されており、壺春堂にも残されています。序を寄せたのは秋櫻子でした。伊昔紅の日記には出征して戦死した兵士の葬儀のために準備されたと思われる弔辞も残され、戦争が身近になってきた様子を物語っています。伊昔紅の日記は大部分が自句の推敲ですが、この年は大阪毎日新聞と東京日日新聞が募集した日の丸行進曲の歌詞への応募原稿、皆野少年消防隊の歌の歌詞、秩父馬酔木会とのキャンプの思い出などが描かれ、伊昔紅とその周辺の様子が分かります。
昭和6年の柳条湖事件から始まった大陸の戦火(満州事変)は昭和8年の塘沽停戦協定によって一度止みますが、昭和12年の盧溝橋事件で再び拡大します。この頃から、新聞社の特派員や出征兵士が前線で作品を詠むようになり、前線俳句と呼ばれました。戦争という非日常的な出来事は、人々の心に根ざしてきた季節感に匹敵するほどの強い言葉(=超季)としてとらえられ、以後、作品の題材として取り上げられるようになります。
超季という言葉のとおり、戦争俳句は当初無季派によって作成されましたが、昭和13年以降、『馬酔木』などの有季派や『ホトトギス』も加わります。美人蕉が戦死した1ヶ月後の『俳句研究』11月号には「支那事変三千句」として百頁にわたって作品が掲載されました。このような動きの中、戦争俳句は前線で詠まれた「前線俳句」、戦場以外の生活を詠んだ「銃後俳句」、ニュースや報道、俳句以外の戦争文学などを通し、戦場の様子を想像して詠んだ「戦火想望俳句」と整理されていきます。一方で、戦争へ一歩ずつ近づいていく時代や社会がおよぼす心の変化を詠んだ俳句があります。中村草田男、石田波郷、加藤楸邨など「伝統、新興の両派を止揚する新しい立場」(座談会「新しい俳句の課題」『俳句研究』昭和13年8月号)と呼ばれた「人間探求派」の作品です。彼らは戦後の中央俳壇をけん引していく存在となります。
昭和15年2月、44名が検挙、拘留された「京大俳句事件」が起きます。取締りを受けた俳誌『土上』が壺春堂に残されています。同誌は大正11年に創刊された俳誌で、当初は『ホトトギス』の流れを汲んでいましたが、嶋田青峰が主宰となった後は新興俳句運動に加わり、無季俳句やプロレタリア俳句にも理解を示しました。同誌の中心である東京三(後の秋元不死男)や古家榧夫はリアリズムを唱えています。
昭和13年から俳誌『成層圏』へ作品を投稿し、竹下しづの女や中村草田男とともに俳句を作り始めていた兜太は、東京帝国大学入学を控えた昭和15年から16年にかけて『土上』へ投句しています。兜太も含め、学生や若者へ理解を示す青峰のおおらかな人柄に魅かれていた若手俳人は多かったようです。昭和16年2月、特高警察により青峰、榧夫、京三は逮捕、拘留され『土上』は廃刊となりました。兜太は後に、「青峰が『同人の二人(東、古家を指す)がリアリズムなんかを言ったおかげでこんなことになってしまった。花鳥諷詠以外の俳句は治安維持法に触れる。異端という考え方が当局にあった。アメリカナイズされた考え方は危ない』とぼそぼそ話していた記憶がある」(『海程』520号)と述べています。
新興俳句運動以降、都市の風景を題材にした作品が多く作られたことはすでに述べましたが、そのなかにはホームレスなどの社会的貧困者や、劣悪な環境下で労働に従事する工場、鉱山、造船労働者を詠んだ作品もありました。『土上』で唱えられたリアリズムは、このような社会の負の側面も含め、作家が持つ社会的な主張や姿勢を、作品を通して表現するものです。東京三はより具体的に、「資本主義の矛盾が生んだ、或いは現に生みつつある諸々の相―人間的な、又は社会的な、都市的、農村的な諸相―」(『土上』昭和12年2月号)を詠むのだとしています。一方で盧溝橋事件以後、国内では戦時体制の急速な整備が進められます。昭和13年に国家総動員法が制定され、翌14年には治安維持法が改定され、国体護持を目的とした取締り対象が大きく広がりました。これ以降、文学作品は制約を受けるようになっていきます。文壇では昭和12年末に反戦を詠った作品を立て続けに発表した『川柳人』が取締りを受けています。俳句でも昭和13年以降急増した戦争俳句の中には、出征した兵士や戦死した兵士の遺族、負傷した兵士などを詠んだ作品が多数ありました。
このようななか、昭和15年12月に虚子を会長とする「日本俳句作家協会」が結成されます。