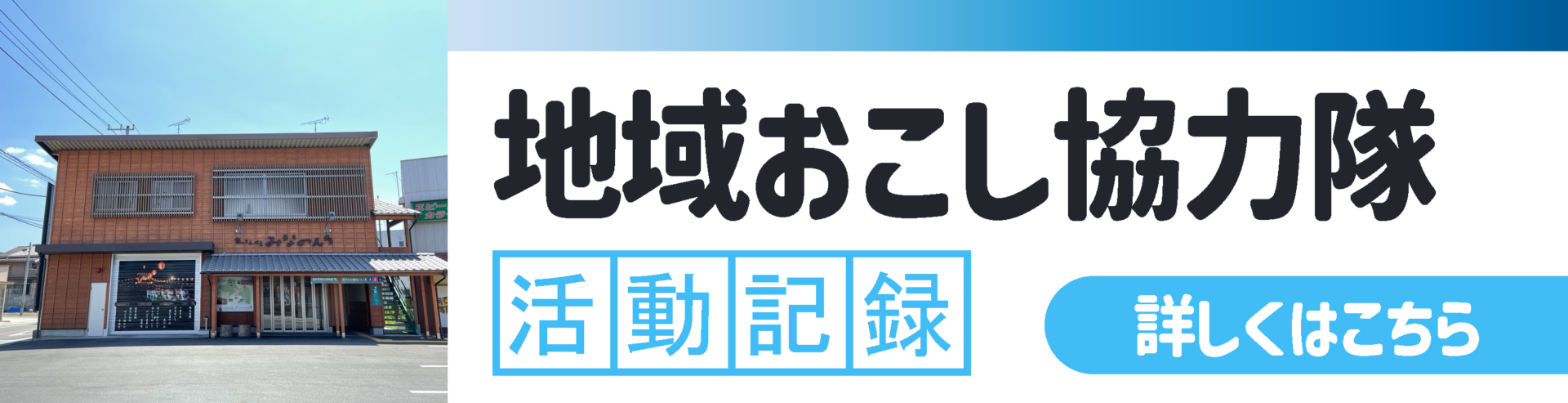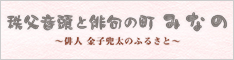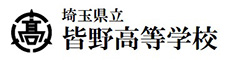新着の行政情報
-
平成27年度 第8回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年12月8日 下日野沢地内防火水槽整備工事 皆野町大字下日野沢地内 指名競争入札 平成27年12月8日 林道雨乞曽根坂線林道改良工事 皆野町大字三沢地内 指名競争入札 […]
-
平成27年度 第7回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年10月26日 水槽付消防ポンプ自動車[水Ⅰ-A型]購入事業 皆野町役場 指名競争入札 平成27年10月26日 小型動力消防ポンプ付普通積載車購入事業 皆野町役場 指 […]
-
平成27年度 第6回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 建設課 橋りょう点検業務委託 皆野町全域 9,014,000 指名競争入札 サンコーコンサルタント株式会社北関東支店 7,7 […]
-
平成27年度 第6回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年9月29日 橋りょう点検業務委託 皆野町全域 指名競争入札 平成27年9月29日 第4分団詰所建設工事 皆野町大字金沢地内 指名競争入札 平成27年9月29日 皆野 […]
-
皆野町いじめ防止基本方針
皆野町では、「心にふるさとと夢を宿し、豊かな心を培う教育と文化の町を目指す皆野教育」を基本方針とし、豊かな心、郷土皆野への誇り、将来への夢と希望をを持った児童生徒を育成すべく、いじめの根絶を含め、様々な取組を進めていると […]
-
平成27年度 第5回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 産業観光課 林道浦山線林道開設工事 大字金沢地内 10,548,148 指名競争入札 守屋八潮建設株式会社皆野支店 10,4 […]
-
生涯学習・スポーツのお知らせ
体育施設利用登録 町営体育施設(町民運動公園・柔剣道場・弓道場)、学校体育施設(体育館・校庭)、スポーツ公園体育施設(野球場・多目的広場・テニスコート)を利用する団体は登録してください。 問合せ 教育委員会社会教育担当 […]
-
平成27年度 第5回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年8月6日 林道浦山線林道開設工事 皆野町大字金沢地内 指名競争入札 平成27年8月6日 林道谷草線舗装補修工事 皆野町大字下田野地内 指名競争入札 平成27年8月6 […]
-
平成27年度 第4回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 総務課 皆野町地域防災計画改訂業務委託 皆野町全域 8,918,000 指名競争入札 地域計画株式会社埼玉事業部 6,280 […]
-
平成27年度 第4回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年6月30日 皆野町地域防災計画改訂業務委託 皆野町全域 指名競争入札 平成27年6月30日 町道皆野49号線測量設計用地調査業務委託 皆野町大字皆野地内 指名競争入 […]