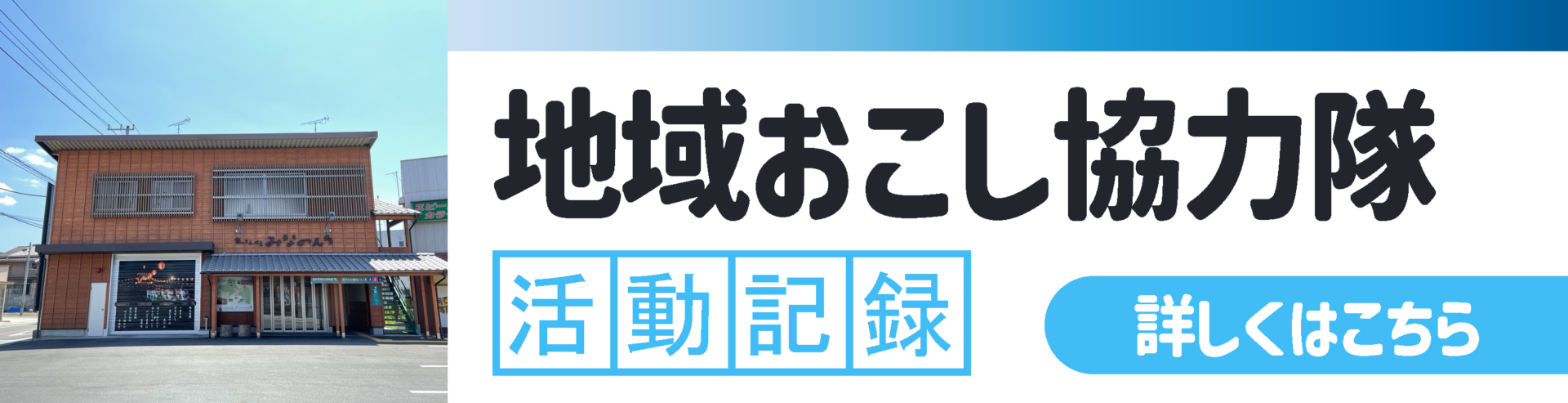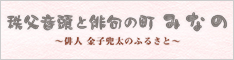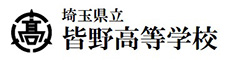新着の行政情報
-
糖尿病性腎症重症化予防治療費助成事業
「糖尿病性腎症重症化予防治療費助成事業」が始まりました。 皆野町糖尿病性腎症重症化予防治療費助成事業が平成28年4月1日から始まりました。 これは、糖尿病性腎症が重症化し透析に移行するのを防ぐため、治療費の一部を助成する […]
-
無料健診(特定健診・高齢者健診)・人間ドック補助実施中!
皆野町では、健診・がん検診が無料で受けられます。 また、人間ドックにかかる費用のうち、3万円を補助しています。 対象者 40歳~74歳の国民健康保険加入の方 75歳以上の方 無料健診(特定健診・高齢者健診)・ […]
-
皆野町「人・農地プラン」
「人・農地プラン」とは 「人・農地プラン」とは、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。 人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について 人・ […]
-
住宅リフォーム補助金
町民が20万円(消費税を除く)以上の住宅リフォーム(改修)工事を行った時に、リフォーム補助金として5万円の助成が受けられます。町民生活の向上及び町内小規模業者の振興を図ることを目的とします。 対象者 皆野町民であり、町税 […]
-
令和4年度 第2回入札結果
第2回入札結果
-
皆野町リノベーション創業支援事業補助金
皆野町内で新規に事業を開始する創業者が、店舗または事業所を新築/増築/改築する工事費を補助します。 対象要件 次の条件をすべて満たすかた 皆野町内で新規に事業(小売業、飲食業、宿泊業またはサービス業等地域経済の活性化に寄 […]
-
母子健康手帳及び妊婦健康診査
母子健康手帳の交付 妊娠したら妊娠届けを健康こども課に提出して、母子健康手帳の交付を受けてください。この手帳は母親の健康状態や赤ちゃんの成長、予防接種などを記録する大切なもので、乳幼児健診や予防接種などを受けるときにも必 […]
-
公共施設等総合管理計画
町の有する公共施設について、保有量の適正化と効率的な維持管理を進め、財政負担の軽減や平準化を図るため、平成28年度に「皆野町公共施設等総合管理計画」を策定しました。また、令和2年度には「皆野町公共施設個別施設計画」を策定 […]
-
皆野町総合振興計画
皆野町総合振興計画について 平成29年4月に平成29年から令和8年までを計画期間とした第5次皆野町総合振興計画を策定しました。 令和3年3月に前期基本計画が終了することから、引き続き町の将来像の実現に向けて、後期基本計画 […]
-
皆野町男女共同参画プラン
男女共同参画社会形成への施策を計画的に推進するため、『第3次皆野町男女共同参画プラン』を策定しました。 第3次皆野町男女共同参画プラン.pdf