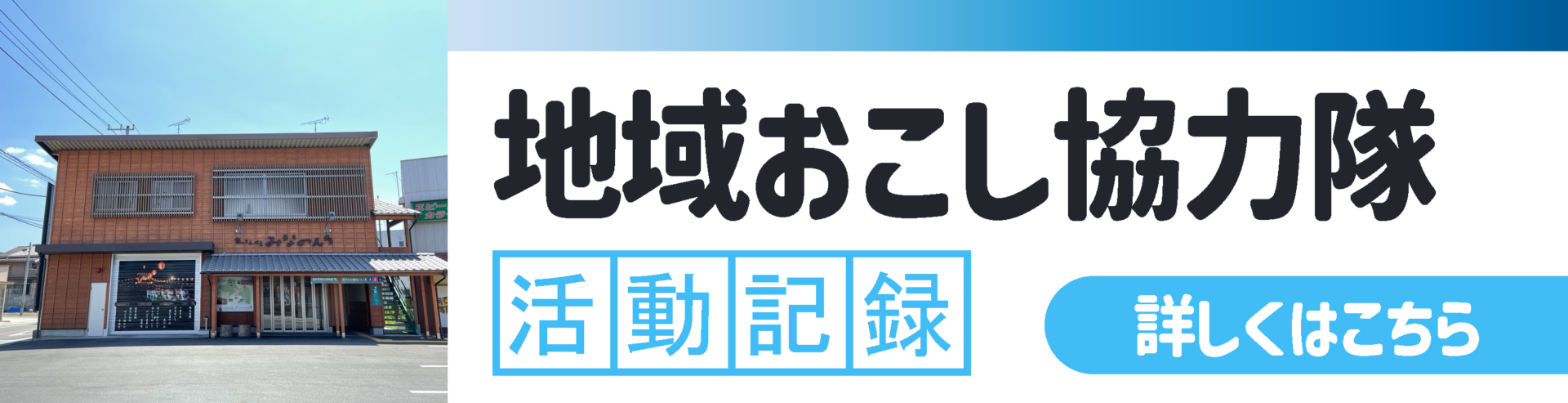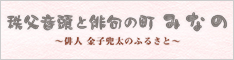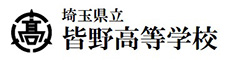新着の行政情報
-
平成28年度 第1回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 教育委員会 皆野中学校物理室空調設備設置工事 皆野中学校内 2,730,000 指名競争入札 (株)電成社秩父支店 2,23 […]
-
平成28年度 第1回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成28年4月21日 皆野中学校物理室空調設備設置工事 皆野町地内 指名競争入札
-
秩父郡市人権に関する意識調査報告書
秩父郡市人権に関する意識調査報告書[pdfファイル](1.16MB)
-
平成27年度 第10回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 総務課 皆野町消防団無線機購入 皆野町役場総務課内 5,030,400 指名競争入札 三峰無線(株)北関東支店 1,899, […]
-
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬(新薬:先発医薬品)の特許期間終了後に作られた薬です。 これまでに使われたことのある薬なので、安心して利用できます。開発コストが少ないので、新薬より安価なのです。利用す […]
-
平成27年度 第10回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成28年2月12日 皆野町消防団無線機購入 皆野町地内 指名競争入札
-
平成27年度 第7回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 総務課 水槽付消防ポンプ自動車[水Ⅰ-A型]購入事業 皆野町役場 23,620,000 指名競争入札 (株)モリタ東京営業部 […]
-
平成27年度 第9回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 健康福祉課 皆野学童保育所外構整備工事 大字皆野地内 3,539,000 指名競争入札 (株)テクノス・アライ 2,980, […]
-
平成27年度 第9回入札予定
入札日 工事名(委託名) 工事場所 備 考 平成27年12月28日 皆野学童保育所外構整備工事 皆野町大字皆野地内 指名競争入札 平成27年12月28日 町道日野沢34号線舗装補修工事 皆野町大字下日野沢地内 指名競争 […]
-
平成27年度 第8回入札結果
工事担当課 工事名 工事箇所 予定価格 契約方法 落札(決定)者 落札(決定) 金額 指名業者 総務課 下日野沢地内防火水槽整備工事 大字下日野沢地内 4,205,000 指名競争入札 (有)小笠原建設 3,600,00 […]