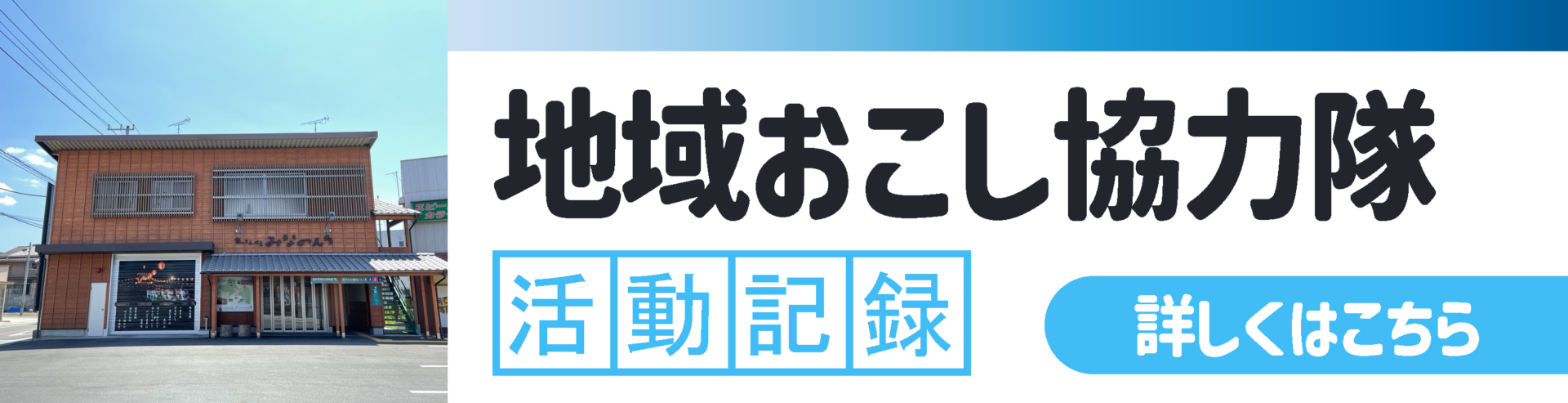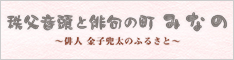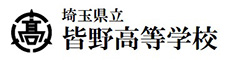県指定文化財 の記事一覧
-
秩父地方の養蚕用具及び関係資料
-
駒形遺跡
荒川右岸に形成された河岸段丘上に位置します。荒川の流水面との比高18.5m、規模は南北300m、東西 120~170mに及ぶもので、発掘調査は3度行われました。第1次調査では、縄文中期の竪穴住居跡3軒、後期の竪穴住居跡1 […]
-
竜ヶ谷城跡
館跡は、外秩父山地、登谷山と二本木峠を結ぶ尾根から派生した尾根の末端、標高360mの頂きを中心に築かれています。東側斜面に多くの遺構が展開し、頂きの郭を囲むように深い堀と土塁が巡らされ、下方に縦堀とそれに交わる堀と土塁が […]
-
勝負沢岩陰遺跡
金沢川の支流勝負沢の右岸に位置し、昭和36年に発掘調査が行われました。洞窟は北東方に15mの間隔を持ち2口開口し、東側を第1洞、西側を第2洞としました。第1洞は、間口3.6m、奥行2.8m、発掘は深さ1.8mに達し、河原 […]
-
門平の虫送り
8月16日に行われます。シンコの笹竹に七夕に作ったノロセと炒りさごを吊し、送り竹を作ります。炒りさごは麦、大豆、粟などを炒り、一つまみの紙捻にしたもので、家族中の体を撫で、体に付いた虫を封じ込めます。各戸から子どもたちが […]
-
立沢の虫送り
8月16日に行われます。七夕飾りを集会所に持ち寄り、長い竿竹に取り付け、先端には幣束を差し込んで3本の梵天を作ります。長老が五色旗と幟旗を用意し、昼食後、集会所に各戸1人ずつが集まり、御神酒をいただいてから、梵天を先頭に […]
-
国神の大イチョウ
国神の大イチョウは、宝登山の麓、皆野町の中心部を一望する妙見平の地に位置している。樹齢700年を越えるといわれるイチョウの大樹は、目通り8.2m、高さ22.7m、枝張りは南北16.3m、東西12.7mを計る。 大イチョ […]
-
金崎古墳群
金崎古墳群は、荒川左岸の河岸段丘上にある群集墳で、かつては8基以上の円墳があったといわれる。しかし、現在墳丘や主体部が残されているのは、大堺1号墳、大堺2号墳、大堺3号墳、天神塚古墳の4基だけである。大堺1号墳を除いて石 […]
-
門平の高札場跡
高札場は、領主が領民に対し禁止事項や法令を徹底させるために、これらの規則を板書きした高札を掲示した場所である。門平耕地のほぼ中央の辻に立てられており、江戸時代の上日野沢村の高札場である。無年貢地として、新設、修理ともに村 […]
-
円墳大塚古墳
秩父市との行政境に近く、荒川右岸に形成された低位段丘に立地している。付近には、中の芝古墳や内出古墳群など数基の古墳が残る。墳丘は、直径約30m、高さ約5mで、墳頂には小祠が祭られている。円礫の葺石で覆われており、墳丘をほ […]