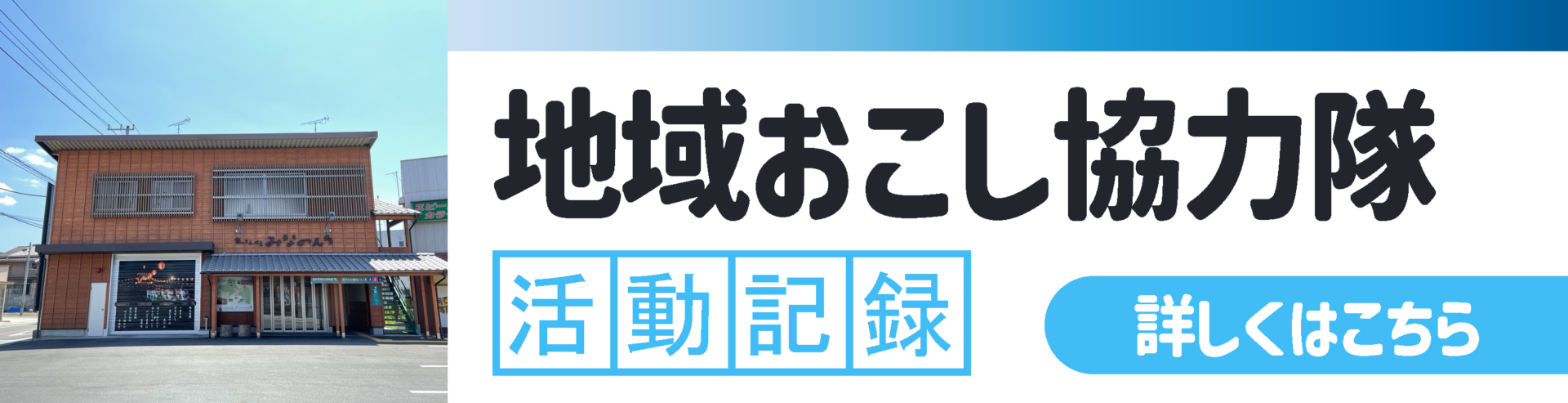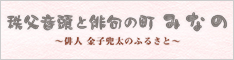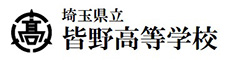新着の行政情報
-
会議施設の利用案内
皆野町文化会館 町の施設をご覧ください 皆野総合センター 町の施設をご覧ください
-
小・中学校
入学通知 毎年4月に小・中学校1年生になるお子さんのいる家庭に、教育委員会から「入学通知書・入学届」を12月初旬ごろに送付します。「入学届」は、教育委員会から指定された小・中学校の入学説明会(一日入学)時に、提出してくだ […]
-
塩旗の五輪塔
五輪塔は、平安中期頃から供養塔、墓石として用いられました。この塔は、室町時代中頃の墓で、地輪に「明応三年(1494)五月一五日□□禅尼」と刻まれています。近くには宝永7年(1710)に建てられた薬師如来が祀られ、健康を守 […]
-
平草のイヌツゲ
イヌツゲは、モチノキ科の常緑低木ですがときに高木となります。この木は根回り2.7m、高さ5.1m、枝張り約六mの巨木です。雌雄異株でこの木は雄株です。5月上旬に開花します。
-
平草のキリシマツツジ
キリシマツツジは、ツツジ科の常緑低木です。指定のツツジはいずれも株立ちで、3本、8本、14本立ちの3株です。高さはそれぞれ1.5mほど、枝張りもそれぞれ東西南北ともに5m。4~5月に紅色のみごとな花をつけます。
-
赤城大神社社叢
社叢というのは「神社の森」のことです。この赤城大神社には、大きく立派な木がたくさんあります。樹齢は特定できませんが、260~270年の歴史を見続けてきた社木です。
-
加増のエドヒガン
若林家では、およそ300年前鑑賞樹として庭に植栽したものと伝えています。樹勢にそれ程衰えを見せず、4月の初め他の桜にさきがけて、5弁の微紅色の花を散形状に5~6付けます。目通り周囲3m、高さ8m、この様な大樹の生存は稀で […]
-
駒形遺跡
駒形遺跡は、北へ向かって流れてきた荒川が、町のほぼ中央部で宝登山にぶつかり、東へ流れを変えた右岸の河岸段丘上に位置します。史跡の範囲は約2,400㎡ですが、遺跡全体の面積は約15,000㎡の広がりを持っています。隣の大背 […]
-
阿佐見氏館跡
館跡は日野沢川左岸に南面した山腹に立地し、傾斜地に築いた石垣は2重3重に巡らされています。その角々には3か所の「食い違い門」が設けられ、石垣の上には更に土塀が続いていたと言われています。石畳もそのまま残り、江戸時代初期の […]
-
小池氏館跡
館跡は、中世の姿をよく残しています。東は蓑山の裾を利用し、背面北側は堀を巡らし、土居をあげた中世の遺構を残しています。庭園は、『新編武蔵風土記稿』に、「郡内第一ノ庭ト云テ、カナタコナタヨリモ游覧セルモノ多ク来ル̷ […]