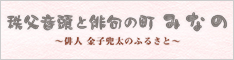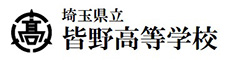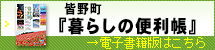有形文化財 の記事一覧
-
薬王寺の十二神将
薬師如来十二の誓願による眷属(お使い)として十二神将があります。薬師如来を信ずる人々を守護する神々で、夜叉大将[やしゃだいしょう]または薬叉大将[やくしゃだいしょう]ともいいます。 薬王寺の薬師堂には最初、室町時代応永2 […]
-
石橋
明治8年調査の「武蔵国郡村誌」の中に「枝野沢橋 前橋の上に架す 長十間巾一丈石橋」とあり、明治8年から改修されることなく使われています。 橋から水面まで約4m、全体が自然石を積み重ねて出来ています。川の床面には敷石(亀腹 […]
-
薬研掘
薬研とは、主に漢方の薬種を細かい粉状にする器具です。V字形で、中が深く窪んでおり、これに薬種を入れ、軸のついた円板状の車輪のようなものをきしらせて押し砕きます。 この堀は、薬研のように石がV字形に積まれているので、長さは […]
-
自性院跡の光明真言塔
光明真言塔の立つ自性院は、明治15年の大渕の大火で類焼しました。 光明真言塔には、円の中心に五文字の光明真言曼茶羅、そのまわりに光明真言の梵字が整然と刻まれています。石塔は、下田野西福寺の光明真言塔と比べ小ぶりながらも滑 […]
-
自性院跡の六面石幢
新編武蔵風土記稿に掲載の大字皆野字親鼻、三光山自性院跡地に残る単制六角幢です。 幢は宝珠が欠失していますが、笠は文字通り単制、幢身は六角で最大幅は39cm、各面には地蔵菩薩が浮き彫りされています。幢身上部に「元禄十五年壬 […]
-
塩旗の五輪塔
五輪塔は、平安中期頃から供養塔、墓石として用いられました。この塔は、室町時代中頃の墓で、地輪に「明応三年(1494)五月一五日□□禅尼」と刻まれています。近くには宝永7年(1710)に建てられた薬師如来が祀られ、健康を守 […]
-
曽根坂一里塚の阿弥陀塔
碑の中央に「南無阿弥陀仏」と刻んであり、塔の左右に「みキハ大ミや」、「ひだり志まんぶ」と書いてあります。右へ行くのが大宮(秩父市)道で、左へ行くのが、四万部(札所一番)道です。この阿弥陀塔は「道しるべ」でもありました。塔 […]
-
曲木の宝篋印塔
この宝篋印塔は基礎が三基積み重ねてあり、別々の宝篋印塔が三基あったことになります。「基礎(1)」には貞治4年(1365)の年号、「基礎(3)」には康暦3年(1381)の年号が刻んであります。貞治4年の宝篋印塔は、曲木に修 […]
-
出牛西福寺の五輪塔
この塔は、室町時代中ごろのお墓で総高97cm、火輪の幅32cm、安山岩を用いています。地輪に「延徳四年(1492)壬子二月十七日元佑法印」の銘文が刻まれています。室町時代のがっちりとした重量感のある形態です。西福寺の寺伝 […]
-
石井家の一石五輪塔
五輪塔は、四つの部分を積んで出来ていますが、この五輪塔は一つの石に全部が刻んであります。一石五輪塔といわれれるのはそのためです。材質はこの付近の砂岩です。高さ43cmと小さなものですが、全体がひきしまっていて重量感があり […]