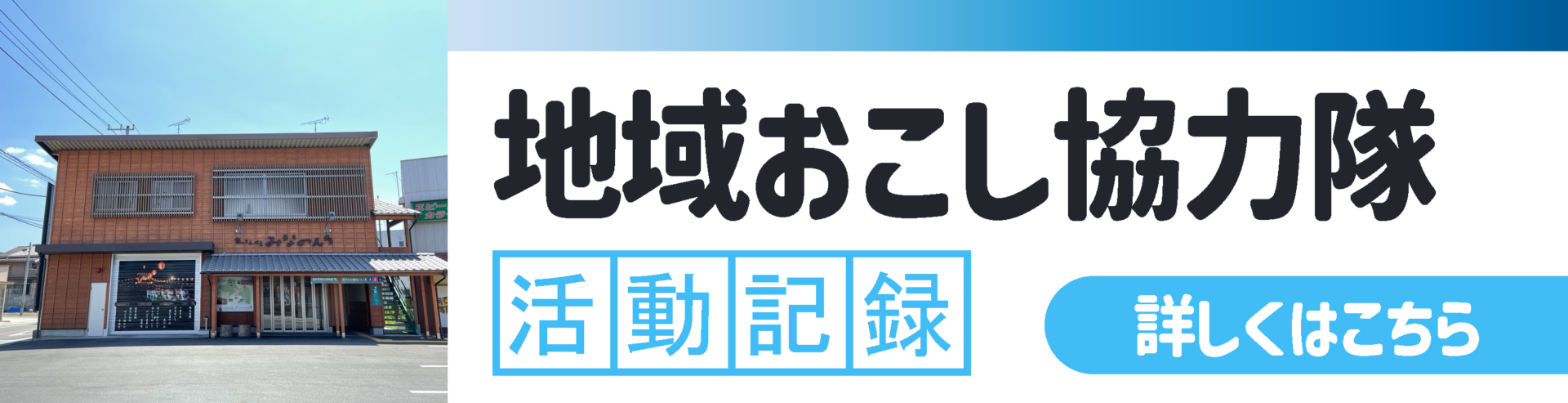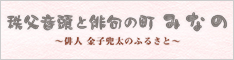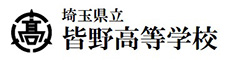有形民俗文化財 の記事一覧
-
皆野町及び周辺地域の灯火用具
民俗学の研究者であった小林拠英氏が収集した灯火用具を、子息で ある小林茂氏が整理するとともに、補充したものです。 資料の総数は295点で、うち124点の収集場所が明らかになっ ています。発火(はっか)、松 […]
-
武蔵川大治郎の碑
武蔵川大治郎は文政6年(1823)三沢の関口家に生まれました。小さい時から体格に優れていて、田舎相撲の横綱になりました。その後、妻や子を残して江戸相撲を志しました。安政6年(1859)に十両、文久3年(1863)には武蔵 […]
-
岩下の庚申塔
庚申塔としては町内屈指のものと考えられ、高さ166cm、幅73cm、厚さ65cmあります。中央に大きく「庚申塔」と彫られ、風格を持った気品のある彫刻です。左の側面に「文化元年(1804)の二月に、亀田鵬斎という学者の書い […]
-
諏訪平の己巳塔
己巳(キシ)の日、講中で集まり精進する行事を巳待講といい、その供養に建てられたものです。甲嶺居士謹書とあり、書、刻とも三沢の野沢禽斎とわかります。背面に「享和二年(1802)壬戌四月金沢邨上郷講中」とあります。石は、金沢 […]
-
住吉社の大絵馬
天沢峠を出牛方面に下がった三差路にある元住吉社遙拝所に掛けられた絵馬で、社の創立縁起を描いた、縦90cm、横190cmの大絵馬です。絵柄は、奥宮の御神体とした「住吉大神」の石碑を担ぎ上げた行列の模様で、土地の若衆中の求め […]
-
正法寺観音堂の大絵馬
「玉とり姫」の物語を絵柄とする縦170cm、横210cmの大絵馬で、勝川春清という絵師の作です。絵師の人物、絵馬の施主、時代などいずれも不明です。正法寺は、往古秩父札所巡礼者が、中山道本庄、上州方面から入る時に最初に立ち […]
-
椋神社獅子頭
真言宗智山派円福寺の土蔵に保管され、戦後、椋神社に移管される時に発見されたのがこの獅子頭です。椋神社は円福寺の鎮守だったと言われ、奉納した獅子舞の道具の内、上郷の一式は円福寺の土蔵に保管されていたようです。獅子頭は3頭あ […]