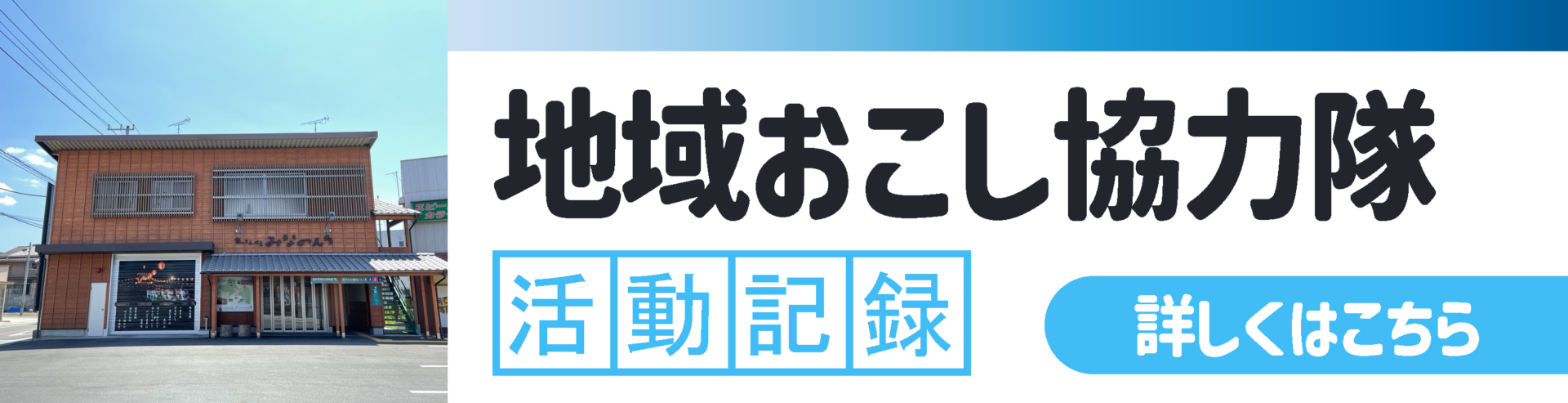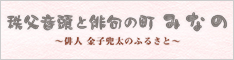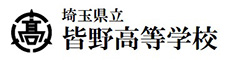町指定文化財 の記事一覧
-
皆野町及び周辺地域の灯火用具
民俗学の研究者であった小林拠英氏が収集した灯火用具を、子息で ある小林茂氏が整理するとともに、補充したものです。 資料の総数は295点で、うち124点の収集場所が明らかになっ ています。発火(はっか)、松 […]
-
薬王寺の十二神将
薬師如来十二の誓願による眷属(お使い)として十二神将があります。薬師如来を信ずる人々を守護する神々で、夜叉大将[やしゃだいしょう]または薬叉大将[やくしゃだいしょう]ともいいます。 薬王寺の薬師堂には最初、室町時代応永2 […]
-
薬王寺のやぐら
「やぐら」は谷間の斜面岸壁に穴を掘ったことから谷倉とも書き、岩倉が転訛したとも言い、物を貯蔵する倉や墓所として利用しています。 特に鎌倉時代から室町時代に山腹を横穴式に掘り、中に納骨したり五輪塔板碑等を納め墓所としており […]
-
旧郷平橋の橋台親柱
この2本の柱は橋の欄干の端につけられたもので、親柱といいます。初代の郷平橋は、明治19年3月に完成の「木鉄混合トラス橋」で秩父新道開削にともない架設されました。わが国の最も古い時代のトラス橋に属するものです。架橋時右岸は […]
-
石橋
明治8年調査の「武蔵国郡村誌」の中に「枝野沢橋 前橋の上に架す 長十間巾一丈石橋」とあり、明治8年から改修されることなく使われています。 橋から水面まで約4m、全体が自然石を積み重ねて出来ています。川の床面には敷石(亀腹 […]
-
薬研掘
薬研とは、主に漢方の薬種を細かい粉状にする器具です。V字形で、中が深く窪んでおり、これに薬種を入れ、軸のついた円板状の車輪のようなものをきしらせて押し砕きます。 この堀は、薬研のように石がV字形に積まれているので、長さは […]
-
三澤村道路元標
明治21年市町村制を公布、22年4月1日施行。自治体がかたまると、次にすすめられたのが村と村をつなぐ道の距離を測るために村内主要道の中心地点を定め、そこに石の標識を設置させました。これを「道路元標」といい全国の村々にたて […]
-
金澤村道路元標
明治21年市町村制を公布、22年4月1日施行。自治体がかたまると、次にすすめられたのが村と村をつなぐ道の距離を測るために村内主要道の中心地点を定め、そこに石の標識を設置させました。これを「道路元標」といい全国の村々にたて […]
-
国神村道路元標
明治21年市町村制を公布、22年4月1日施行。自治体がかたまると、次にすすめられたのが村と村をつなぐ道の距離を測るために村内主要道の中心地点を定め、そこに石の標識を設置させました。これを「道路元標」といい全国の村々にたて […]
-
自性院跡の光明真言塔
光明真言塔の立つ自性院は、明治15年の大渕の大火で類焼しました。 光明真言塔には、円の中心に五文字の光明真言曼茶羅、そのまわりに光明真言の梵字が整然と刻まれています。石塔は、下田野西福寺の光明真言塔と比べ小ぶりながらも滑 […]